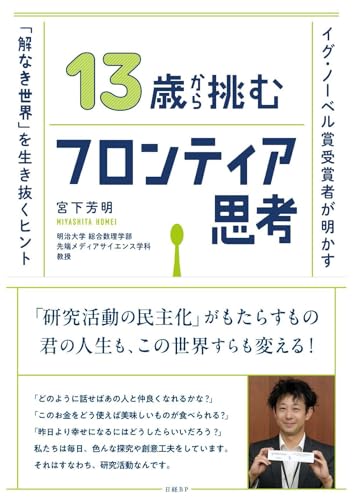かつて地球には、私たちとはまったく異なる人類が生きていた――。赤道直下から北極圏まで駆けまわり、30年にわたり洞窟の地面を掘り続けた、第一人者にして考古学界の異端児による初の一般書。
4度の日本アカデミー賞に輝いた著者による「映画音楽講義」がついに刊行。なぜあのシーンにこの音楽なのか? プロの考える 「劇中音楽」 の作曲術、演出効果を学び、映画に隠された「音の設計図」を鑑賞する。
昆虫学という学問が存在しないなか独学で研究を行い、小さな虫の中に「神」を見た女性、マリア・シビラ・メーリアンとは何者だったのか──。科学と芸術が混じり合った豊かな時代の輝かしい偉業を、中野京子が生き生きと蘇らせる。
近代知の起源とされる「啓蒙思想」は、ヨーロッパ貴族のサロンではなく、じつはマダガスカルの海賊と女性たちの社会実験によって創造されたのではないか。海賊王国の知湧き心躍る「本当の」歴史をたどり直し、自由、国家、民主主義をめぐる無数の常識をくつがえす。
1968年にフィンランドへ渡り、日本人初のマリメッコ・デザイナーとして活躍した、脇阪克二。フィンランド、ニューヨークを経て60歳を過ぎて京都へ戻るまで、一つのことを長く続けてきた彼が、何を見てどう動き、何を大切にしてきたのか。
宇宙からの眼で、古代の都市や遺跡、当時の環境を探ることで、時間を越えた世界を見ることが容易になってきた。「宇宙考古学」と呼ばれる地球観測技術で解き明かされた古代エジプト、古代中国の研究成果を、第一線の研究者たちが熱く語り明かす。
現役時代から少数意見を多数表明してきた元最高裁判事の著者が、退官後もその立場を貫き執筆した憲法論文の集大成。司法はなぜここまで立法・行政に対して謙抑的なのか? 日本の司法消極主義を批判し、本来の司法の在り方を問う。
ロングトレイルほど求道的ではなく、かといって山頂を目指す登山でもなく、かといって散歩ほどゆるく短い歩行ではない。都会の散歩よりももっと深く濃い自然に浸り、とはいえつらくならない程度に、ただ歩く喜びを満たす旅。「フラット登山」の旅へようこそ!
ポーランドの国家プロジェクトとして五ヵ年計画で進められている『源氏物語』全巻の翻訳から何がわかってきているのか。その全貌とその翻訳手法・論点を明らかにする。
ビッグバンの後、最初に誕生した恒星を観察するために開発された最新の宇宙望遠鏡、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。この望遠鏡による太陽系、恒星、深宇宙、銀河、系外惑星、ブラックホールなどの観測結果から、さらに将来へのミッションまでを観測写真、解説図などとともに展開。
ドン・キホーテのデザイン統括責任者・二宮仁美が、創業以来、初めて明かす店舗デザインの秘密。700以上の店舗デザインを手がけた著者が、「なぜ人々が思わず入店したくなるのか?」かを解説。
自分の「関心ごと」をテーマにしたボードゲームづくりは、人生をもっとワクワクさせてくれる最高の探究活動です。50種類以上のボードゲームを企画開発、製作してきた著者による「ボードゲームづくりの教科書」。
注意力散漫、移り気、そそっかしい……その「弱点」が「能力」になる。なぜ人類にADHD(注意欠如・多動症)という「能力」が残ったのか? 読めば生きづらさが強みに変わる、世界的ベストセラー!
西欧絵画の遠近法と異なる中世イコンの「逆遠近法」を解き明かしたことで知られ、美学のみならず神学、化学、工学、集合論・数論における多彩な業績を残すも、スターリン体制下で銃殺されたフロレンスキイ。知られざる「ロシアのレオナルド・ダ・ヴィンチ」の思想に迫る。

![[図説]映画音楽の教科書 名作からシーンごとの音の役割を読み解く [図説]映画音楽の教科書 名作からシーンごとの音の役割を読み解く](https://m.media-amazon.com/images/I/51OTVqRpfbL._SL500_.jpg)